BLOG ブログ
Web広告→実店舗への集客をより効果的に。「diggin」が進めるO2O向けWeb広告とは

Web広告を見た人のうち、実際にどれくらいの人数が店舗に来てくれたのか? 来店者数の把握は、デジタル施策による効果的な店舗集客を行うための第一歩。しかし従来型のWeb広告だけでは来店数を計測することができず、きちんと把握できていないという企業が多いのではないでしょうか。
西川コミュニケーションズでは、実店舗を持つ企業の販促施策やマーケティングのサポートを進める中で、来店単価を指標とした集客強化のためのデジタル広告施策を実現してきました。2023年7月にはその業務を引き継いだグループ会社「diggin(ディギン)」を設立。O2O※専業のWeb広告代理店として、さらに実績を積み重ねています。
今回はそのdigginの代表取締役 社長 川村起市に、店舗集客に特化したWeb広告の仕組みとメリットについて聞きました。
※O2O:Online to Offline。オンライン(Web)からオフライン(実店舗)へ誘導し、購買へとつなげるマーケティングの手法。
実店舗を持つ企業が抱える、Web広告の課題とは
―――なぜ、実店舗を持つ企業向けに特化したWeb広告が必要なのでしょう? 店舗型ではない企業などのWeb広告との違いについて教えてください。
川村: 消費者へのアプローチとしてデジタル施策が主流となった現在、Web広告はどの企業にとっても重要なものです。O2Oへの注目度も高まり、販売店や飲食店、クリニックといった実店舗を持つ企業でも、来店誘致の施策としてWeb広告を利用されている企業は多いですよね。
しかし実店舗の場合、ECサイトなどと違って、Web広告にどれだけの集客効果があったのかがわかりづらいという問題があるんです。
―――わかりづらさの原因はどこにあるのでしょう?
川村: 通常、Web広告は広告をクリックした先のランディングページ(企業のサイトやキャンペーンの特設ページなど)に、効果指標となる計測ポイントが設定されています。どれくらいの人数が広告からそのサイトに遷移したのか、その人たちがサイト上でどんな行動をとったのかなどを計測して、広告の効果を測っているわけです。
これがECサイトなら話は簡単です。広告経由でやってきたユーザーからどれだけの売り上げが上がっているのか。新規の受注1件あたりにどれほどのコストがかかっているのか。集客から売り上げまでがWeb上で完結しているため、広告の費用対効果が明確に数字で把握できます。
ところが、実店舗をもつ企業となると、費用対効果の計測に必要なのは店舗への来店者数です。Web上の計測ポイントだけでは、広告を見た方のうち何人が実際に店舗に来てくださったのかまではわからないですよね。
―――来店というリアルな行動が、Web上では計測できないということですね。
川村: とはいえデジタル施策を何もしないわけにはいきません。結果として、正確な集客効果が見えていないのにも関わらず、「効いているだろうから続けよう」という消極的な運用になってしまっている企業が少なくないんです。
もちろん成果指標を定めてしっかり計測されている企業もあります。ただその場合も指標はサイトの閲覧数やお問い合わせ数などである場合が多く、店舗への集客効果までは正しく把握できていないのではないでしょうか。
実店舗を持たない企業と同じような、Webサイト閲覧への誘導&Webフォームのコンバージョン取得という手法では、デジタル施策と実際の集客の間にどうしても溝ができてしまうんです。
―――その溝を超えるために、O2Oに特化したWeb広告が必要ということですね。
川村: まずは「どの施策によって」「どの時期に」「どの店舗に」「何人が」来店誘致できたのかを把握し、来店一人あたりにかかったコスト=「来店単価」を見える化することが重要です。そのうえでさらに広告を最適化していくことで、来店単価を指標とした、実店舗での集客強化に直結するデジタル広告施策が実現します。
digginでは、この見える化と最適化をふたつの柱としたO2O向けのWeb広告を提供しているんです。
見える化を実現する「Google来店計測」
―――では、その見える化について聞かせてください。どうやってWeb広告から実店舗へ来店誘致できたかを計測するのでしょうか?
川村: digginがお勧めしているのが「Google来店計測」です。広告をクリックした人がその後に来店したかどうか、スマートフォンのトラッキング※により計測するサービスです。
※トラッキング:行動を継続的に追跡し、分析すること。
- 広告をクリックしていない、見ただけの人も計測可能。
- 従業員や通行人とみなされた人数はカウントから除外されます。
- スマートフォンの位置情報の利用を「許可しない」に設定にしている方も除外されます。
- そのほかGoogleが定める厳しいプライバシー保護基準をクリアしたユーザーをベースに、欠落データは推定で補いながら来店者数をカウントします。
―――計測はどれほどの精度が見込めるんでしょうか?
川村: そこは皆さん気にされるところですよね。もちろん計測できない場合もあり、欠落した部分があれば推定で補われてカウントされているとなると、やはり実際の来店者数との乖離があるのでは、という疑問をいただくこともあります。
そこでdigginでは、クライアントにご協力をいただいて独自に検証を行いました。クライアントが店舗に設置しているシステムから把握できたリアルな来店者数と、Google来店計測の数値を比較してみたんです。
リアルな来店者数はWeb広告を見ていない人も含むため、当然そちらの数値のほうが高くなります。しかし、Google来店計測の数値が多い月は、実際に店舗を訪れた来店者数も多く、逆にGoogle来店計測の数値が少ない月はリアルの来店者数も少ないというふうに、双方の数値の上下の動きが増減の幅も含めて一致していたんです。
この検証でGoogle来店計測の数値と実際の来店者数にはっきりした相関関係が認められました。来店単価の指標として十分に使える精度だと自信を持ってお勧めしています。
―――しかし、それほど高い精度で来店者数が把握できるなら、この来店計測がO2O広告のスタンダードになっているのでは? 多くの店舗が来店者数を把握できていないのはなぜなのでしょう。
川村: 広告予算が大きなハードルになっているんです。一定金額以上の広告出稿がなければ計測ができないという仕組みになっているものですから。
閾値は取得できた来店データ数によって変動しますが、例えば自動車ディーラーの場合、来店計測ができるようになるには広告予算が月に数百万円必要です。計測できている企業もあるかとは思いますが、一般的にはかなり高いハードルですよね。実際、広告代理店から来店計測を提案されても、予算が合わず見送ってきた企業は多いのではないでしょうか。
―――ではdigginでも来店計測は十分な予算をお持ちの企業へのご提案になるのでしょうか?
川村: いいえ、digginの強みは、予算に関係なく来店計測を実施いただけることにあるんです。
計測可能かどうかの閾値は、クライアントや広告ごとのものではなく、Googleの広告アカウントごとのものです。つまり、同一のアカウントで複数の広告を出稿し、その全体量で閾値を超えていれば、計測が可能になります。digginでは、自社が保有するアカウントに複数のクライアントを束ねて出稿することで、この予算ハードルをクリアしているんです。
なお、このGoogle来店計測は、Googleビジネスプロフィールというサービスとの連携が必須になっています。digginではこのGoogleビジネスプロフィールも活用して、さらに来店誘致の効果を高めることをお勧めしています。
来店誘致の効果を高める「Googleビジネスプロフィール」
―――Googleビジネスプロフィールとは、どのようなサービスなのでしょう。
川村: Googleでお店などを検索した際、検索結果のページにお店の写真やメニューなどの情報が表示されますよね。あの表示領域がGoogleビジネスプロフィールです。店舗側がメンテナンスをしない限りは、Googleがお店のサイトなどから自動的に情報を収集して作成しています。
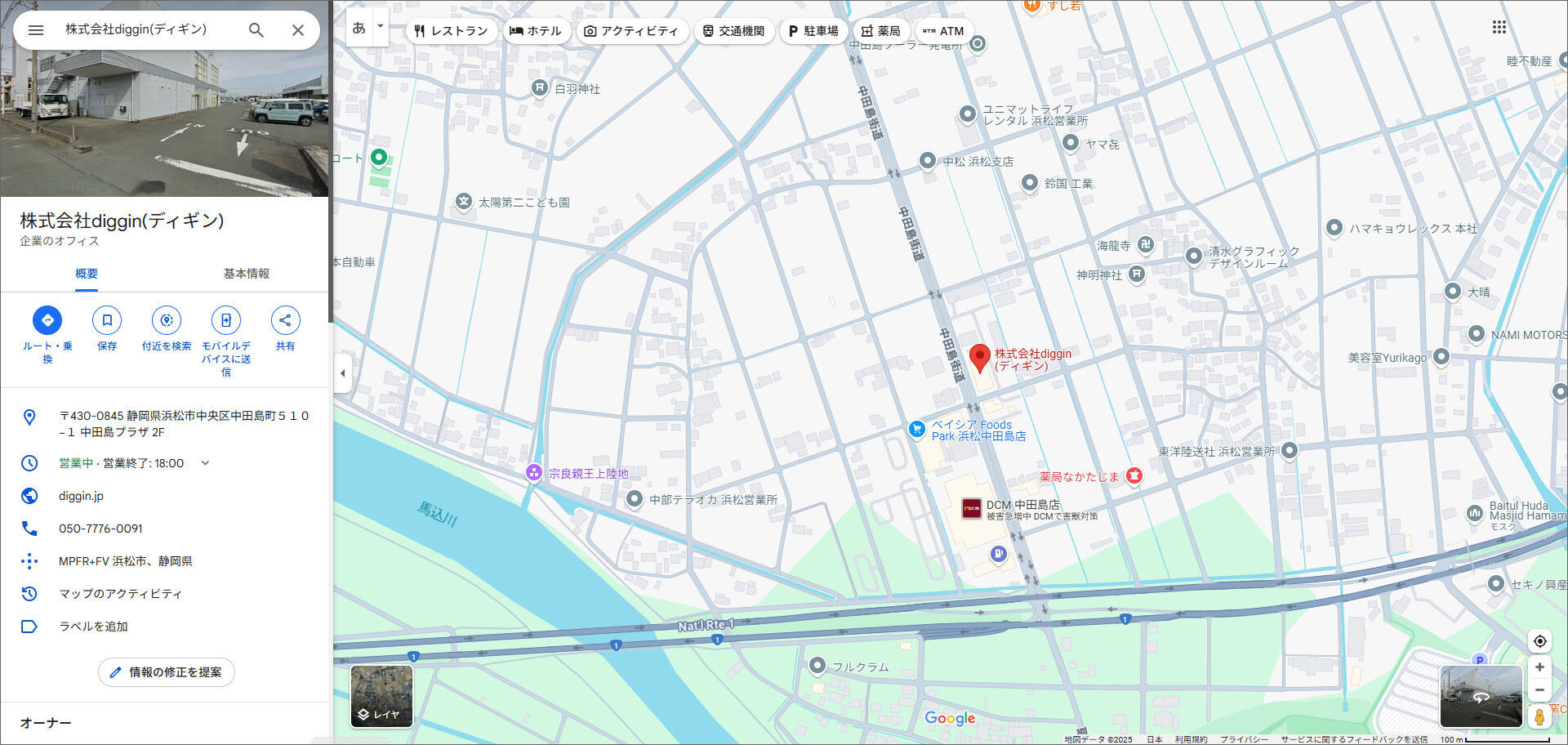 Googleビジネスプロフィールの表示例
Googleビジネスプロフィールの表示例
表示自体は無料ですし、来店計測はアカウントに紐づけするだけで可能ですが、きちんと店舗の魅力を伝えていくにはここのメンテナンスも重要です。私たちはこのGoogleビジネスプロフィールの活用も、サービスとして提供しています。
Googleビジネスプロフィールの活用サービス例
・日々更新される店舗情報(カテゴリ・サービスメニュー・商品登録・写真・説明)の一括管理/メンテナンスの代行
・店舗のイベント情報やお知らせの投稿
・写真・360度インドアビュー・動画の投稿 など
―――お店を探そうとして検索する人によく見られる場所ですから、確かに来店への影響力は大きいですね。
川村: そうなんです。一方で、不適切な情報が掲載されているとかえってボトルネックになりやすいところでもあります。
メンテナンスをしない限りは自動で作成されるものなので、誰かが撮影したよくわからない画像が使われていたり、定休日や営業時間などの大切な情報が間違っていたり。また悪意のある第三者がデータの改ざんを行い、フィッシング詐欺に使われた事例もあるんです。
―――きちんとメンテナンスをして、正しい情報を掲載しておくことが、来店誘致には重要ということですね。
川村: イベントや季節ごとのお知らせなど細かな更新をしていくことで、より来店誘致の効果を高めることもできます。情報のメンテナンスがしっかりされていれば、検索結果で上位に表示される可能性も高まりますので、MEO※対策という点でも大変な影響力がある部分です。
※MEO:Map Engine Optimization(マップエンジン最適化)。Googleマップなどの地図の検索結果で上位に表示させることを目指してさまざまな施策を行うこと。
しかし、特に何十もの店舗を持っているような企業ともなると、ひとつひとつメンテナンスしていくのはなかなか難しいですよね。そこでdigginでは、このGoogleビジネスプロフィールのメンテナンスも代行しているんです。
―――メンテナンスをするとしないとでは、どれほどの違いがあるのでしょう?
川村: クライアントにご協力いただいて、ビフォーアフターの効果計測をしたことがあります。
自動収集された情報のみの状態から、写真や情報を投稿して手を加えたあとで、来店率がどう変わったかを計測してみました。結果、もっとも変化があった店舗ではWeb広告の来店単価が+40%改善するという効果が見られました。影響の大きさを実感しましたね。
来店誘致をAIで最大化する「P-MAX for store goals」
―――では、次に広告配信の最適化について教えてください。こちらはどのように実現しているのでしょう?
川村: 私たちがお勧めしてきたのは「P-MAX for store goals」という、これもまたGoogleの広告商品のひとつです。
大きな特徴は、Googleの5大プラットフォームをまたいで配信できること。そしてプラットフォームのどこに何を配信するのか、どんなユーザーに広告を出すのかを、AIが自動で最適化してくれること。これにより、従来は点でしか捉えることができなかったユーザーを面として捉えることができ、来店に向けた最適な広告配信が可能になります。
P-MAXの中にも複数のメニューがあり、中でも「P-MAX for store goals」は効率のよい来店誘致を実現できる広告になっています。
特徴①5大プラットフォームをまたいだ配信
検索、ディスプレイ、YouTube、Googleマップ/Googleビジネスプロフィール、GmailのGoogleの5大プラットフォームをまたいで広告を配信できます。
特徴②最高峰のAIによる、来店に特化したターゲティング
どのプラットフォームにどの広告を表示させるべきか、「もっとも来店確率の高い配信パターン」をAIが学習し、自動で広告を配信します。
P-MAX配信パターンの学習イメージ
―――「どこに」だけではなく「なにを」「いつ」「誰に」までAIが判断してくれるんですね。
川村: そうなんです。従来型のディスプレイ広告などでは、プラットフォームごとに個別に出稿していますよね。カスタマージャーニーのそれぞれのタッチポイントに合わせて、このプラットフォームにこの内容の広告を表示させようと狙ってひとつずつ設定しています。
対してP-MAX広告は、AIが最適と判断したプラットフォームに、あらかじめ用意しておいた素材を組み合わせて広告を表示させられます。例えば最初に動画で興味を持ってもらい、最終的にGoogleマップで来店へと促すといった配信パターンの効果が高いと判断されれば、そのパターンで配信していく。ユーザーの興味度合いに応じた情報提供を行うという、ナーチャリング的な要素もAI機械学習が担っているわけです。
カスタマージャーニー全体に網をかけて、ユーザーが情報を欲するタイミングに自動で広告を出すことができるんですよ。
―――そういったパターンを見つけるのは、人力ではたいへんな手間とセンスが必要ですよね。そこをAIが判断してくれるというのは便利です。
川村: 最高峰のAIを持つGoogleならではのサービスですね。Web広告でよりよい効果を上げるためには細かな調整が必要ですが、AIを活用することでよりスピーディに最適なパターンを見つけることができます。P-MAX広告を数多く扱ってきた私たちには、そのAIを扱うノウハウがあります。
AIの活用はどの分野でも急速に進んでいますが、Web広告も例外ではありません。digginでは、さらに以下のデータ活用サービスとも組み合わせて、AI機械学習の強化を進めています。
Googleカスタマーマッチ
自社が保有する個人データを広告配信に利用する、Google広告のターゲティング機能のひとつ。例えば企業が持つ顧客リストをGoogle広告に取り込んで、よりパーソナライズされた広告を配信していくことができます。
GA4リマーケティング
Webサイトのアクセス状況を分析できる「Googleアナリティクス」のオーディエンスデータを広告に取り込むことで、より精度の高いターゲティングが可能になる機能です。
企業内には質のいいデータが豊富にあるのに、うまく活用されていない場合が非常に多い印象です。Googleアナリティクスも多くの企業が導入しており、せっかくデータが蓄積されているのに、サイト計測以外のことに活かせている企業がどれほどあるでしょう。こういったデータを広告と共有することで、さらにAI機械学習を強化していくことができます。

O2O専業のWeb広告代理店「diggin」のこれから
―――digginが扱う広告商品はそのほかにもあるのでしょうか?
川村: 必要に応じてさまざまなサービスをご提案していますが、中でもこれからお勧めしていきたいのが、2023年10月に正式リリースされたGoogle広告の新商品「デマンドジェネレーション」です。
P-MAX広告が「成果(ゴール)を最大化」するのに対し、デマンドジェネレーションは「新規顧客を獲得」するのに特化したAI広告商品です。ショート動画を含むYouTubeやGoogleアプリ、Gmailといった、視覚的かつ娯楽性の高い配信面に動画広告を掲載できます。
これまでP-MAX広告ではカバーしきれなかった領域をカバーできるものとして期待しています。P-MAX広告と組み合わせたり、使い分けたりすることで、より効果的な集客を実現していきたいですね。
―――これまでお聞きした来店計測やP-MAX広告を含め、O2O向けといっても特にどの業種が向いているなどはあるのでしょうか?
川村: 特に業種は限定していません。ただ、中でも大きな成果が出せるのではと考えているのは、新車ディーラー、中・小規模医療機関、クリニック、不動産(住宅展示場・マンションモデルルーム)、飲食店(中~小規模チェーン店)、小売り・流通業界、神社仏閣などですね。
―――実店舗を持ち、来店型のビジネスをされている企業ならば、どこでもサポートできるということですね。では、最後に今後の展望について聞かせてください。
川村: 市況感の低迷からデジタル広告業界の横ばいが続いてきた中でも、digginは2023年7月に西川コミュニケーションズからスピンオフして以降、広告取り扱い額を大きく伸ばしてきました。
これまで積み上げてきた多くの企業様のサポート実績、そして最新のテクノロジーを活用するスタンスは、さまざまなクライアントのご要望にお応えできるものと自負しています。

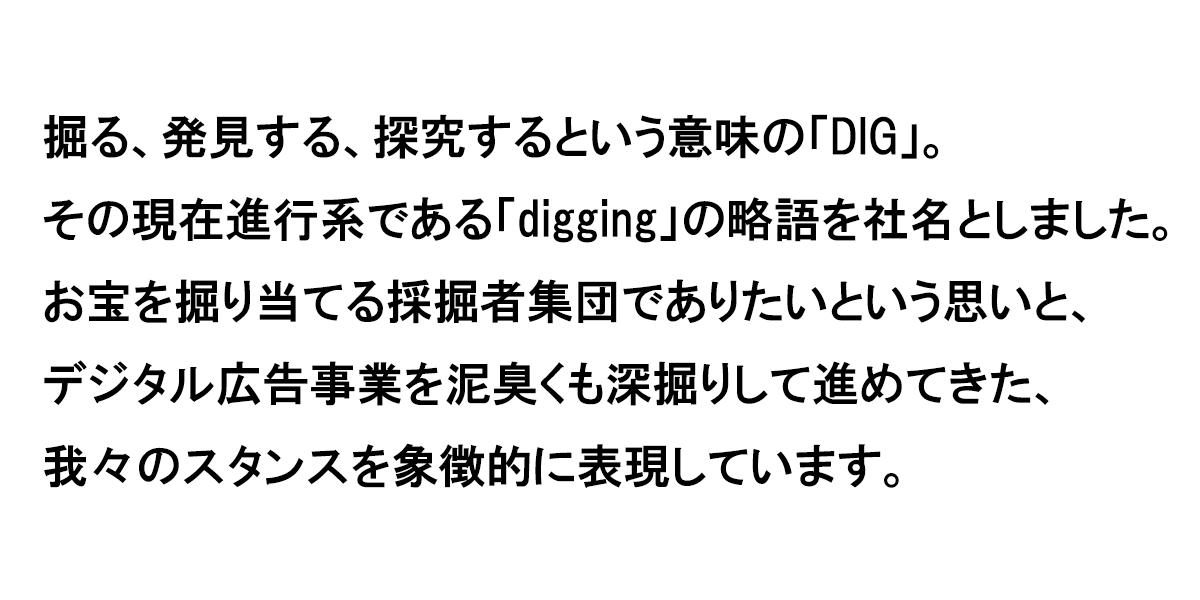
diggin公式サイトはこちらから
株式会社diggin(ディギン)
これまで予算の面から来店計測ができるウェブ広告を見送ってきた企業様でも、我々ならもっと低いご予算で提案可能です。来店単価を指標とした、集客強化に直結するWeb広告施策にご興味のある方は、ぜひ下記フォームからお問い合わせください。
GoogleおよびGoogleロゴおよびGロゴ、Google検索およびGoogle検索ロゴ、YouTubeおよびYouTubeロゴ、GoogleマップおよびGoogleマップロゴ、GmailおよびGmailロゴ、GoogleビジネスプロフィールおよびGoogleビジネスプロフィールロゴは、GoogleLLCの商標または商標登録です。
O2Oに特化したWeb広告について、お問い合わせはdigginサイトからどうぞ
お問い合わせ川村起市
株式会社diggin 代表取締役 社長 前職では家電系ISPでポータルサイトの媒体開発・マネタイズ業務に従事。 NICO入社後は、主に自動車業界の得意先を担当しながら、新規事業の立ち上げを推進。
マーケティングカテゴリのブログを読む
-
Web広告×Googleマップで集客強化。実店舗の集客を支援する二社連携の取り組みとは
2025.06.25
-
狙いはファン獲得。企業と顧客のコミュニケーションツールとしてのノベルティとは
2024.09.26
-
「Cookie廃止撤回」へとGoogleが方向転換。Webマーケティングの今後に変化はあるのか?
2024.08.29
-
Webアクセシビリティの現在地 〜よりアクセシブルなWebサイトであるために~【第1回】
2024.05.21
-
Webアクセシビリティの現在地 〜よりアクセシブルなWebサイトであるために~【第2回】
2024.05.21
-
販促施策に隙間を作らない。トータルサポートの精神から始まった、浜松支社の動画制作とは
2023.11.14
-
ターゲットの見極めが成功のポイント よりよい定性調査のための基礎知識
2023.05.19
-
リアルとWebのアクセシビリティへの取り組みを実感する
2022.11.18


